マイブームの押井守
先日善照寺に悪巧みに伺った時、時間つぶしに入った宮脇書店で
偶然見つけた新書
同じ作者の「凡人として生きるということ」は実はipadで読んでいたんだけど
これが、便利なようで記事を書こうとするとページをペラペラとめくれないので不便この上なくて
でも、紙の本をアマゾンでわざわざ買うのは、ちょっとなぁって気分だったんだけど
偶然見つけたので、これは誰かが読んどけって言ってくれてるんだということで
購入してすぐ読了
コミュニケーションを通した日本人論
[amazonjs asin=”434498255X” locale=”JP” title=”コミュニケーションは、要らない (幻冬舎新書)”]コミュニケーションには2つの側面がある
コミュニケーションには2つの側面がある。と僕は思っている
ひとつは「現状を維持するためのコミュニケーション」で、もうひとつは「異質なものとつきあうためのコミュニケーション」だ。
(コミュニケーションは要らないより)
日本人はこの2つのうち、「現状を維持するためのコミュニケーション」を偏重し過ぎているっていうのが書き出し
そちらに偏重するのは、ある種農耕民族のサガのようなモノで
水稲が発達して、あとはやるだけっていう状況にあったら
そうした「馴れ合い」のコミュニケーションで適度に刺激しながら、重要なことは「わかっているだろう」で済ませるほうが効率がいい
でも、それは狭いコミュニティだから成り立ってた話で、それを国全体にも適用しようとしたから日本はおかしくなっただろうって話
あいまいな表現が、地域の効率化に役立っていたはずなのに
その場しのぎで論議を避けて責任から逃れる言い訳としか使われなくなってしまった
異質なものとつきあうためのコミュニケーション
これの重要性は、つい最近強く感じた
moimoimoiの活動を通して、取注さんとしらさわさんという全く異質な人たちと作品を作っていて
自分では、うまいこと2人とコミュニケーションを取っているつもりだったけど
それは「現状を維持するためのコミュニケーション」で体制を繕っていただけだったと反省している
僕は「摩擦を恐れずに自分を論理的に主張して新しい関係を模索する」ことを(無意識だけど)さけていたようだ
その結果、今回のmoimoimoiの作品は、まとまりのないものになってしまい
取注さんとしらさわさんの持つ「面白さ」のみしか残らないものになってしまった
書き言葉と話し言葉
ロジックとしての言語とは、平たく言えば「書き言葉」のことだ。
人間は書き言葉で文章を書くことでしか論理的にものを考えるという思考回路を身につけることができない。
(コミュニケーションは要らない より)
英語に比べて、日本語は曖昧な表現が多いとよくいうけど、それは話し言葉でのことで
例えば、論文みたいな書き言葉は曖昧性は認められない
そういう書き言葉が日常で使われなくなってしまって、話し言葉でしかコミュニケーションしなくなってから
話し言葉によるその場しのぎでないコミュニケーション「異質なものとつきあうためのコミュニケーション」がなくなってしまったのではないか?とのこと
そういうコミュニケーションのためには、書き言葉のようなロジカルさが必要なんだ
それは、ネットとSNSの登場でさらに加速しているようで
twitterでもFacebookでも(特にtwitterに多いけど)話し言葉しかない
それは原理的にロジカルではありえないんだ
ネットやSNSでコミュニケーションが増えたとか言われているけど
大多数の人にとっては、「異質なものとつきあうためのコミュニケーション」の能力を衰退させてしまうものなのではないか
このブログだって、似たようなものではあるんだけど
一応修士まで学校にいっているおかげで、なるべくロジカルに書こうと努めているから
読みやすいエッセイによくあるように、ロジカルな物語の中に、ちょっとだけ自分の言葉を交ぜるぐらいにしようと頑張ってみている
そのおかげで、なんとか自分の思考の整理ぐらいにはなっている気がする
僕は会社員だから・・・
こうやって、整理していかないと、創作をするときに武器にできないんだろう
なんていっても、日常がクリエイターではないし、平凡なんだから
なんとか、文章にして整理して、武器にして、活用していく
そうやって攻めていくしか、僕が創作とか表現を実現していく方法はないのかもと思ったりしている
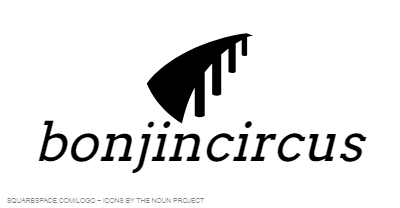







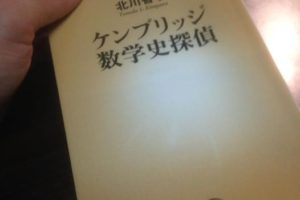
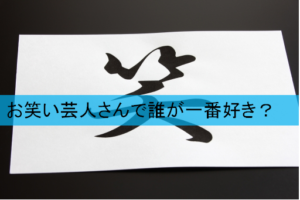
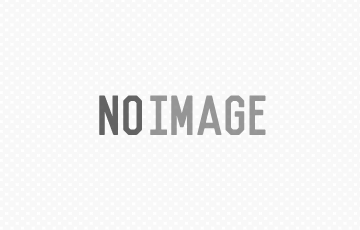
コメントを残す