最近僕の思考は、養老孟司の唯脳論的思想にのまれつつある
[amazonjs asin=”4480084398″ locale=”JP” title=”唯脳論 (ちくま学芸文庫)”]この唯脳論という本は、唯物論や唯心論のように、その題名を手放しで心棒するものではなく
唯脳論という考え方があると仮定すると、こういうことが考えられないだろうか?という
ある種、唯脳論批判みたいなモノで、要は人間は脳で考えたことがすべてだと思い込みやすいけど
実は身体ってものがあるんだよーって本なんだけど、この考え方が結構わかりにくい
かといって僕なんかが解説してみてもわかりやすくなるモノでもないんだけど
ちょっと唯脳論的な例えが思いついたから、書いてみる
僕の中の「炎」
僕の中で炎は、主にボーイスカウトの時のイメージが強い
ボーイスカウト活動のキャンプで仲間と一緒に「たちかまど」と呼ばれる竹で組んだかまどを作って
料理を食べ終わって、特にすることがなくなっても、テントには戻らずに延々と火を見ながら語り合う
僕は会話を持たせることが昔から得意じゃないんだけど、火の前だとそんなことは関係ない
村上春樹の短編集かなんかで「焚き火のファンは5万年前から世界中にいたよ」というセリフがあったけど
火というのはただ静かに見ていても全く飽きない
それはある種、頭(=脳)が作り出した言葉ではなかなか表現出来ない魅力がある
エネルギーを放出しているように見えて、全てを包み混むような安心感があって
調和がとれているように見えるのに、急に崩れたりする様子が愛おしい
と書いてみても、うまく表現出来ているとは到底思えないけど
結納論でいうところの、脳が言語で名付ける以前に存在している身体で感じる感覚としての美しさがそこにあるんだと思う
[amazonjs asin=”4101001502″ locale=”JP” title=”神の子どもたちはみな踊る (新潮文庫)”]僕の中の「燃えるぜ!」
一方で僕の中の「燃えるぜ!」というセリフは、脳が言語で名付けたものである
小さい頃から、アニメや漫画で聞いていた「燃えるぜ!」というセリフやその背景の集合体であり
本来は「炎」と大きく関わっている言葉のはずだけど
僕の中の「燃えるぜ!」という概念は上記の火の美しさとは全く接点がない、別の概念だ
登場人物がただ単にテンションが上がって言ってることでもあるし
捨て身で後先を考えずにエネルギーをぶつける前に言ってることでもある
「燃えるぜ!」というセリフを聞いて、「炎」の感覚的な美しさを思い出すことは全くない
本来「炎」の様子をさして表現していたはずの言葉を
抜き出して一部だけを乗せた概念を「アニメや漫画」という媒体から受けすぎて
言葉が「アニメや漫画」限定の言葉として、僕の中で「炎」の概念と切り離されて形成されてしまったのだ
[amazonjs asin=”4086179091″ locale=”JP” title=”ジョジョの奇妙な冒険(第3部) スターダストクルセイダーズ 文庫版 コミック 8-17巻セット (化粧ケース入り) (集英社文庫―コミック版)”]「炎」を取り戻そうとする宮崎駿
だからと言って「炎」が手放しで尊くて「燃えるぜ!」がダメなのかと言ったらそうでもない
たとえ話の中でさらにたとえ話をして申し訳ないが
例えば、アニメ映画監督の宮崎駿は、この例の「炎」を取り戻そうとしているようだ
本当に生きているような実感を持った表現を好んでいる宮崎駿は
スタジオジブリのアニメーターの描く絵を自分で書き直してしまっていたらしい
情報化が進む世界で、アニメーターも感覚が身体から離れてしまったから
宮崎駿本人のような実感を持った絵というのが描けなくなってしまっていたのだろう
[amazonjs asin=”B000ARV0FW” locale=”JP” title=”ハウルの動く城 DVD”]「燃えるぜ!」を引用する押井守
逆に押井守は、その名付けられた言葉の引用を使って世界を構築しようとする
攻殻機動隊なんかは自分の身体を失って、義体と呼ばれる人口の身体を持った人々のストーリーだ
どこにでもあるような中途半端に情緒豊かな体裁を取っているアニメとは違って
どこまでも情緒を排除して、誰かによって名付けられた言葉である引用によって世界観を作ることで
情報化による身体の喪失を感じながら、身体を喪失した人間の新しい発見というものを目指そうとする
[amazonjs asin=”4062205092″ locale=”JP” title=”攻殻機動隊 DVD BOOK by押井守 GHOST IN THE SHELL (講談社キャラクターズA)”]何を求めて生きていくのか
皆が「炎」のような身体を失っていって、「燃えるぜ!」のような名付けられた概念に染まっていく中で
何を求めて生きていけばいいのか
なんとか身体を取り戻そうと努力して生きていくいくべきなのか?
身体を取り戻すために養老孟司が提案するように、田舎に行って自然にふれあう時間を取ってみようか
でもそれをしたからって何も見えなくて、そのせいで仕事を首になったりしたらどうするよ
身体を捨ててしまって、人間が情報であるかのような方向性を求めて生きていくべきなのか
少し前に「人間も所詮情報でしかないし」みたいな文言を見たし
でも、ヒトのゲノム解析は終わったかもしれないけど、まだ発見されてない別の分析項目が出てきたらどうするよ
そんな、脳か身体か?っていう問いかけを考えていくこと自体がとても最近好きなんだ
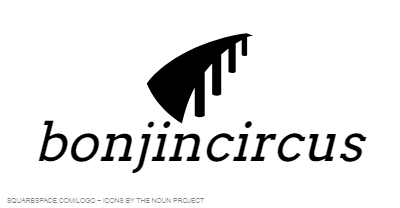

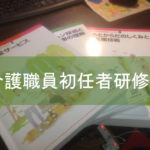
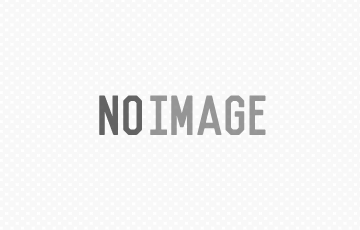



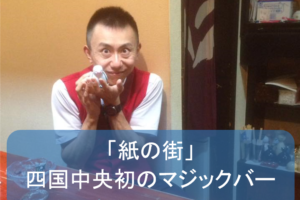
コメントを残す